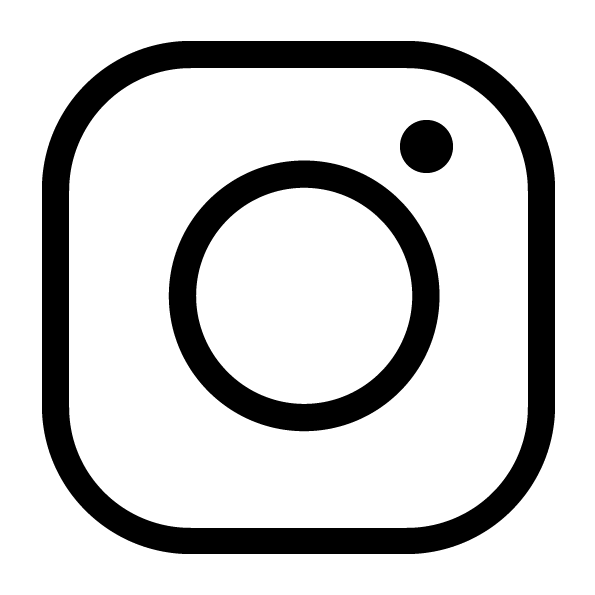小腸内細菌異常増殖症とは、Small Intestinal Bacterial Overgrowthの略で、SIBOと呼ばれることもあり、小腸内の細菌が過剰に増えることで体に様々な不都合な症状や栄養吸収の障害、また全身への免疫系への異常まで起こす状態です。
十二指腸・空腸は無菌か、腸内溶液1ccあたり細菌(Lactobacillus,Enterococcus,グラム陽性の好気性,通性嫌気性菌)などが104 CFU(Colony forming unit(コロニー形成単位)の略で、生菌数を表す単位)程度認められます。Bacteroidesなどの偏性嫌気性菌は認められません。遠位回腸は、近位小腸と大腸の中間的な特徴をしめします。上部小腸内容液1ccあたり105CFU以上の細菌の存在がSIBO診断の目安とされています1)。上部消化管における細菌特に嫌気性菌の増殖は、糖や食物線維などを発酵して炭酸ガス、水素ガス、メタンガスの発生から腹部膨満につながります。メタンは腸管通過時間を延長させます。同時に産生される短鎖脂肪酸も消化管ホルモンPYY(peptide YY)を誘導し消化管通過時間を延長させます2)。そのためSIBOの症状として特に頻度が高いのは腹部症状で、具体的には腹部膨満感、下痢や便秘、腹部不快感、腹痛、ガス(おなら)の増加などがあります。また、細菌が大切な栄養素を分解するためにビタミン不足などの栄養障害や胆汁酸の組成の変化などで脂肪の吸収障害などが起きます。また小腸上部の粘膜バリアの障害による細菌の全身への侵入や、免疫活性の賦活化により全身の影響も考えられています。例えば線維筋痛症や慢性疲労症候群などです3)。
ある研究では自覚症状のない健康成人の4 % にSIBOが認められ、過敏性腸症候群と診断された人の86 %4)にSIBOが認められたという結果があり、稀なものではないと考えられます。
SIBOの原因としては以下のものが考えられています1)。
- 胃酸分泌の減少:PPIの投与や、萎縮性胃炎による酸分泌不全による小腸上部のアルカリ化
- 膵液の減少:慢性膵炎などによる膵液の減少が上部小腸の細菌を増やす。
- 胆汁の減少:胆汁の減少が上部消化管の細菌を増やす。
- 小腸の動きの低下:膠原病の強皮症などのように小腸の動きが低下すると細菌が増えやすくなる。
- 回盲弁の機能低下:大腸からの逆流が増えて細菌も逆流する。
- 小腸上部の免疫能の低下:IgA欠損症やその他の免疫異常など。
SIBOの診断には空腸内容液の細菌学的検索が理想的ですが日本では保険適応がなく実施している施設も研究目的だと思われます。そこで水素またはメタン呼気試験が用いられます。ラクツロースを摂取した後、呼気に含まれる水素、メタンの量をガスクロマトグラフで分析する方法です。ヒトはラクツロース(二糖類)を消化できませんが、腸内細菌はラクツロースを分解します。健常人ではラクツロースが結腸に到達し初めて大腸内細菌により分解され水素またはメタンが生成されます。この水素やメタンは吸収され肺から呼気として排出されます。これに対し、SIBO患者では,ラクツロースは上部消化管で増殖した細菌によって分解され、呼気テストにおいて水素が2つのピークとして検出されます。ラクツ
ロースを使った呼気テストの他に、ブドウ糖(グルコース)を使った呼気テストがありますが、ブドウ糖の吸収は迅速なため十二指腸や近位空腸におけるSIBOの発見には有効ですが、遠位小腸のSIBOを見逃す危険性が指摘されています。ラクツロースを用いた呼気試験の感度と特異度は52%と86%とされています2)が、実際されているところは少ないと思われます。
SIBOの治療は、好気性および嫌気性腸内細菌の両方をカバーする経口抗菌薬の10~14日間投与が行われます。経験的治療として、以下のうち1つまたは2つを使用します。
アモキシシリン/クラブラン酸500mg,1日3回(有効率50%)
セファレキシン250mg,1日4回
トリメトプリム/スルファメトキサゾール160/800mg,1日2回(有効率95%)
メトロニダゾール250~500mg,1日3回または1日4回(有効率「43~87%)
シプロフロキサシン 500 mg 、1日2回(有効率43~100%)
リファキシミン550mg,1日3回の単剤投与(有効率61~78%)またはフラジオマイシン500mg,1日2回との併用。
*有効率は文献1)より参照しましたがおのおの大きなばらつきがあります。
リファミキシンは腸で吸収されない合成抗菌薬で、細菌学的にSIBOで80 % 有効で、症状の改善率は33 ~ 92 % に認められます1)。
しかし抗生剤投与による小腸の殺細菌は、大腸の常在菌を乱す可能性があり、また耐性菌の出現や偽膜性腸炎の発生などのリスクがあり慎重に適応を絞るべきと考えられます。
腸内の細菌は脂肪をあまり利用できずに糖類を利用するため、炭水化物を避けて、脂肪を多く摂取したり、低 FODMAP 食にするという方法も理論的には考えられますが、しっかりしたエビデンスはまだ示されていません1)。ビフィズス菌などのプロバイオテイクスの摂取は有効性を示す論文もあります1)。糞便移植の有効性も報告がありますがまだこれからの課題と思われます1)。
私達一般臨床家は、不定の腹部症状を見たとき、SIBOを念頭におきPPIの中止なども考えるべきでしょう。
令和7年10月24日 菊池中央病院 中川 義久
参考文献
1)Mark p et al : Small Intestinal Bacterial Overgrowth . Am J Gastroenterology 2020 ; 115 ; 165 – 178 . | DOI: 10.14309/ajg.0000000000000501
2)安藤 朗ら:腸疾患における腸内細菌のかかわり . 日内会誌 2013 ; 102 ; 2983 – 2989 .
3)Henry C et al : A Framework for Understanding Irritable Bowel Syndrome. JAMA. 2004 ; 292 ; 852-858. doi:10.1001/jama.292.7.852
4)過敏性腸症候群と低FODMAP食